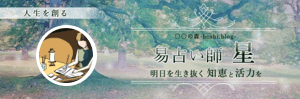こんばんは。
〇〇の森-hoshi.blog-の星です。
今回は、自分でも易を勉強してみたい!という方のために
「易をつくった人たち」
についてお伝えしていきたいと思います。
易の世界は
歴史が長くて奥が深いので、土台の部分から理解していこうとするととても時間がかかりますし
挫折の原因になります。
ですので
分厚い本を読む時間がない方📚や
長時間勉強するのは苦手💦
という方は、ぜひこちらの記事を気が向いたときに少しずつ読んで、歴史や成り立ちなどを覚えて行ってくださいね。
易を作った人たち
易を作った主な人物は、おおまかには全部で3人います。
その3人のことを、まとめて易聖(えきせい)と呼ぶこともあります。
易聖(えきせい)の3人について
・伏羲(ふくぎ)
一番初めに易の世界を整えた人は、伏羲(ふくぎ)と言います。
この方は、約1万年前の王様とされる人物です。
(情報によっては、神話に出てくる想像上の人物としているものもあります。)
この方が、いまに通じる「64掛」を作ったとされています。
他にも、今でいう天気予報の文化をつくったり、人々が食料を得やすいように、魚を捕る網を発明し
人々に畜産や漁を教えたとされます。
・周文王(しゅうぶんおう)
その次に易の世界に関わってくれたのは、周文王(しゅうぶんおう)という人です。
今も通じる、易の掛辞(かじ)や爻辞(こうじ)を作りました。
それぞれの掛や、爻についている短い説明文のようなものですね。
そして、この方は周の時代の人なので周文王とよばれていて、いまの「周易」はここからきていると言われています。
・孔子(こうし)
3人目の易聖(えきせい)は孔子です。
孔子が、これまでの易にさらに情報を加えて、研究を行いました。
孔子の働きにより易伝の書き増し作業が行われて、内容がぐっと増えて、今の全体像が作成されました。
いかがでしょうか?
もちろん上に示した3人以外にも、たくさんの人の手や解釈を経て、易は発達・発展し成長してきました。
今回の記事を読んで
すこしでも皆さんの興味を満たすことが出来たり、学びを楽しいと感じていただければ幸いです。
易は、
これまでに様々な人により研究され、書き増され、解釈が増え、成長し、変化してきましたが
もともとはるか昔から、ずっとずっと私たちの心の中に存在していた概念のような気がしています。
今も
その概念を必要とし、信じる者の心の中に
必要とされればいつも、姿をあらわし道を示して下さる概念のように日々感じています。
易は
文字や紙がない時代から、すでに存在していたとされています。
易でよく使う概念である、陰–と陽ーの概念が、文字ではなくこのようなシンプルな模様になっているのもそのためです。
文字がなくても、木の枝などで概念を示すことができるためです。
紙がなくて(あるいはとても高級で)竹にほったり、石にほったりして情報を後世に伝えないといけない場面でも扱いやすいように出来ています。
今日も楽しんでいただけたら、ぜひいいね👍などの反応をお願いします。
こんなふうに勉強をつづけていきたい!という方も反応をいただければ励みになります。
いつも、ありがとうございます。
〇〇の森-hoshi.blog- 星